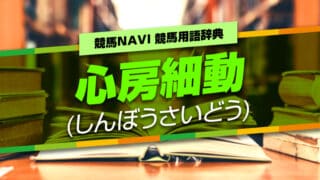 し
し 心房細動(しんぼうさいどう)
心房が規則正しいリズムを失う不整脈の一種でレース中に発症することが多く、発症すると急激に失速してしまう。人間の心房細動とは異なり、健康な馬でも突如発症することもある。ほとんどは一過性のため、自然治癒して再発しないことが多い。
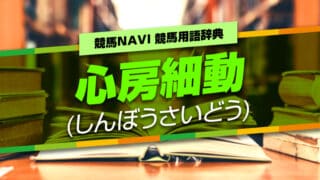 し
し 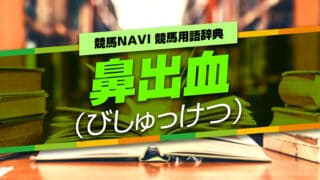 ひ
ひ 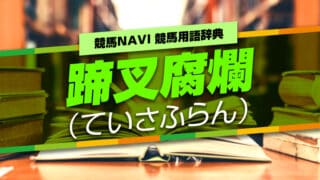 て
て 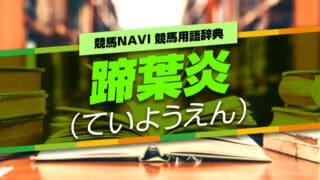 て
て  て
て 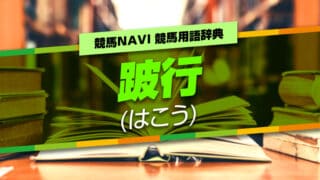 は
は 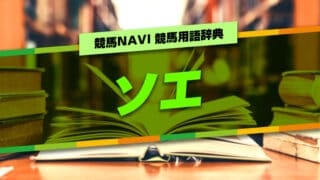 そ
そ  ひ
ひ  せ
せ 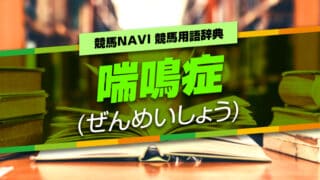 せ
せ